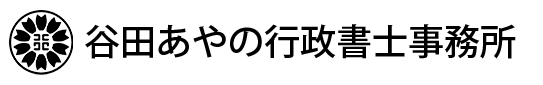当事務所における「障害」の表記について
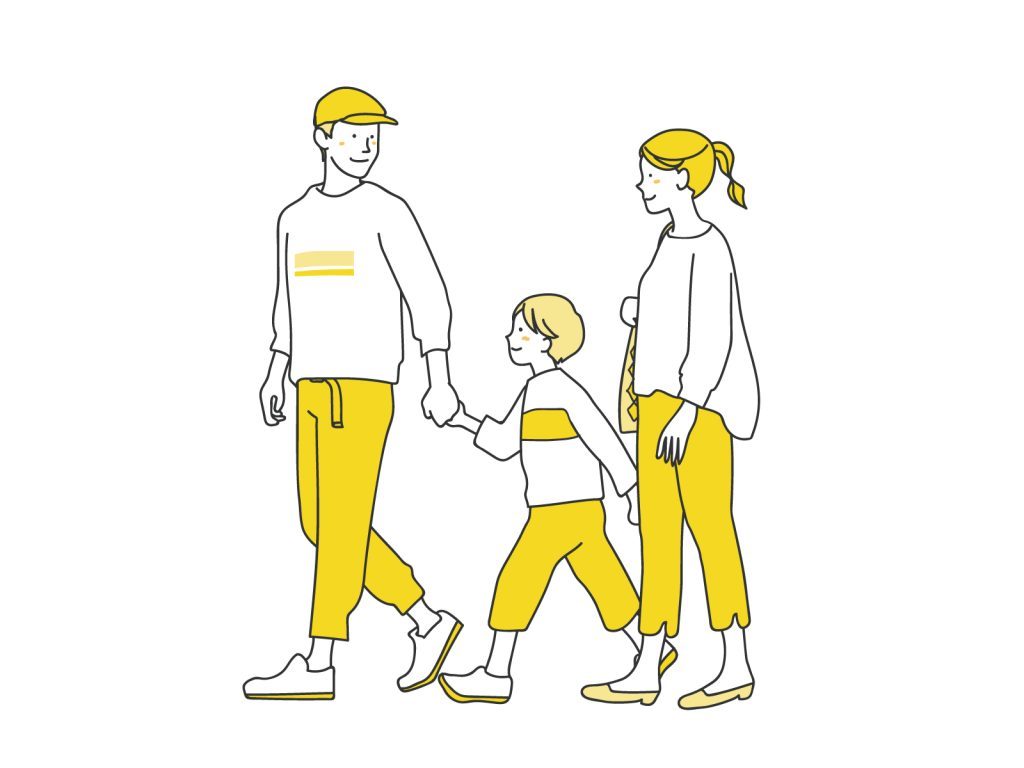
「障害」「障がい」「障碍」…。皆さまは、どの表記を使っていますか?
どれが正しくて、どれが間違い、というものでもありませんが、それぞれの書き方によって、イメージが違ってくることと思います。
内閣府「障がい者制度改革推進会議」でも、結論出ず
少し前になりますが、2009年(平成21年)~2010年(平成22年)のあいだ、国もこの表記について検討会議をしていました。この3通りの表記それぞれのプラスイメージ・マイナスイメージがヒアリングされ、さらには、「碍」という字を常用漢字にするかどうか、という検討もされていたようです。
そして、それぞれの考えに基づいて様々な表記を使っている状況において、内閣府は「現時点において新たに特定のものに決定することは困難であると言わざるを得ない。」という結論に達しています。国も「コレに統一しよう!」という結論には至らなかったわけです。
自治体によって対応はさまざま
NHKの「放送用語委員会」の見解
NHKでは、東京オリンピック・パラリンピックを前に、「障害」の表記について検討がされてきました。
そして、2019年11月の検討会では、
・原則「障害」・必要に応じて「障がい」を使うこともできる。
・固有名については「障がい」「障碍」を使うこ
ともできる。
・上記の事項は,今後も実情に応じて不断の見直しを行う という見解に達しています。
実際の東京パラリンピックの競技放送では、テロップや字幕などで「障がい」と表記されました。これは、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の表記に合わせるためということで、競技放送以外ではパラリンピックのニュースを含め、従来通り「障害」とされました。
この日会見した正籬(まさがき)聡放送総局長は、用字用語はNHKの放送用語委員会で検討しているとした上で「社会情勢によって移ろったり使い方が変わったりすることもある。今回に限らず、常に状況を見ながら不断に考えていく課題」と述べています。

言葉は移り変わるもの
それぞれの言葉のもつニュアンスやイメージは、社会的な意識のなかで変化していくものだと思います。それぞれの表記の認知度や違和感も、移り変わっていくでしょう。
当事務所の考え方
当事務所では、原則「障害」の表記を使用していますが、今後の流れに応じて、常に検討の姿勢を持ち続けたいと思っています。